看護レポートの書き方:事例、構成、ポイントを徹底解説
看護師、看護学生の皆さん、日々の臨床実習や学習で感じたこと、学んだことをレポートにまとめるのに苦労していませんか?このガイドでは、分かりやすく、論理的な看護レポートの書き方を丁寧に解説します。実習で得た経験を効果的に伝え、先生を納得させ、さらに自身の看護スキル向上に繋げるためのノウハウを詰め込みました。
看護レポート作成の基本:構成と書き方
看護師、看護学生の皆さん、日々の臨床現場での学びを形にする看護レポート。しかし、いざ書こうとすると、どこから手をつければ良いのか、構成はどうすれば良いのか悩むことも少なくありません。この章では、看護レポート作成の基礎となる構成と書き方について解説します。レポート作成の目的を明確にし、論理的な構成を理解することで、あなたのレポートがより効果的に伝わるものとなるでしょう。
レポートの目的と種類
看護レポートには、様々な目的と種類があります。それぞれの目的に合わせて、レポートの構成や記述方法を使い分けることが重要です。主な目的としては、以下のようなものが挙げられます。
- 実習報告:臨床実習での経験を記録し、学びを深めるため
- 事例研究:特定の患者さんの看護を通して、看護過程を深く理解するため
- 文献レビュー:特定のテーマに関する文献をまとめ、知識を整理するため
- 研究論文:看護に関するテーマを研究し、新たな知見を得るため
レポートの種類によって、求められる内容や構成が異なります。例えば、実習報告では、具体的な事例を通して得られた学びや反省点を中心に記述します。一方、事例研究では、看護過程に沿って、患者さんの状態や看護介入、その評価を詳細に記述する必要があります。それぞれの目的に適したレポートを作成することが重要です。
基本的な構成要素(導入、本論、結論)
どのような種類のレポートであっても、基本的な構成要素は共通しています。それは、導入、本論、結論の三つの部分です。それぞれの部分で何を記述すべきか理解し、論理的な構成でレポートを作成しましょう。
- 導入:レポートの目的や背景、概要を説明します。読者の興味を引きつけ、本論への期待感を高める役割があります。
- 本論:具体的な事例やデータに基づいて、詳細な内容を記述します。看護過程に沿って、患者さんの状態、看護介入、評価などを論理的に説明します。
- 結論:レポート全体のまとめとして、得られた結論や考察、今後の課題などを記述します。自分の学びや反省点を客観的に評価し、今後の成長に繋げるための重要な部分です。
これらの構成要素を意識し、それぞれの役割を理解することで、より分かりやすく、説得力のあるレポートを作成することができます。
適切な言葉遣い
看護レポートでは、正確かつ客観的な言葉遣いが求められます。専門用語を適切に使用し、主観的な表現は避け、事実に基づいた記述を心がけましょう。また、誤字脱字や文法の誤りがないように、必ず見直しを行いましょう。
- 客観的な表現:「~と思われる」ではなく、「~と観察された」など、事実に基づいた表現を心がけましょう。
- 専門用語の正確な使用:専門用語の意味を理解し、正確に使用しましょう。
- 丁寧な言葉遣い:敬体(ですます調)で記述し、読者への配慮を示しましょう。
適切な言葉遣いをすることで、あなたのレポートの信頼性が高まり、読み手への理解を深めることができます。

事例の記述方法:具体例とポイント
看護レポートにおいて、事例をどのように記述するかは、あなたの考察の深さや学びを示す上で非常に重要です。単なる出来事の羅列ではなく、患者さんの状況を的確に捉え、自身の看護実践を具体的に示すことが求められます。ここでは、事例記述の具体的な方法と、押さえておくべきポイントを解説します。
事例選択のポイント
まず、どのような事例を取り上げるかが重要です。全ての事例をレポートに記載することは現実的ではありませんので、以下の点を考慮して、最も伝えたい学びや経験を象徴する事例を選択しましょう。
- 重要な学びが得られた事例: 自身の看護観やスキルに大きな影響を与えた、印象深い事例を選びましょう。
- 看護過程が効果的に展開できた事例: アセスメントから評価まで、一連の看護過程を詳細に記述できる事例は、あなたの理解度を示します。
- 困難を乗り越えた事例: 困難な状況にどのように対応し、解決策を見出したのかを具体的に記述することで、あなたの成長をアピールできます。
- 患者さんのQOL向上に貢献できた事例: 患者さんの視点に立ち、どのような支援が効果的だったのかを具体的に記述しましょう。
客観的な事実の記述
事例を記述する際には、客観的な事実を正確に伝えることが重要です。主観的な解釈や憶測ではなく、観察した事実、患者さんの言動、検査結果などを具体的に記述しましょう。客観的な記述は、あなたの考察の信頼性を高めます。
- 患者さんの状態: バイタルサイン、全身状態、意識レベルなどを具体的に記述します。
- 実施した看護ケア: 具体的な処置内容、患者さんの反応、使用した物品などを詳細に記述します。
- 患者さんの言動: 患者さんの訴え、表情、行動などを具体的に記述します。
- 検査結果: 血液検査、画像検査の結果などを数値で示します。
これらの情報を正確に記述することで、第三者が読んでも状況を理解しやすくなります。客観的な事実に基づいた記述は、あなたの看護判断の根拠を明確にし、レポートの質を高めます。
患者のプライバシー保護
患者さんの事例を記述する際には、プライバシー保護に最大限配慮する必要があります。個人を特定できる情報(氏名、住所、生年月日など)は絶対に記載してはいけません。
また、他の患者さんの情報や、患者さんのプライベートな情報は、必要最低限に留め、個人が特定できないように配慮しましょう。以下に、プライバシー保護のための具体的な対策をいくつか示します。
- 氏名や個人情報は伏せる: イニシャルや仮名を使用する、年齢や性別のみを記載するなど、個人が特定できないように工夫しましょう。
- 病室や病棟をぼかす: 具体的な場所を特定できる情報は避け、「〇〇病院の〇〇科」など、大まかな情報に留めましょう。
- 写真や動画の利用を控える: 患者さんの顔が写った写真や動画は、本人の許可を得ていない限り使用しないようにしましょう。
- 情報管理を徹底する: レポートは、個人情報が漏洩しないように、厳重に管理しましょう。
これらの対策を講じることで、患者さんのプライバシーを守りながら、効果的な事例記述を行うことができます。

看護過程に基づいたレポート作成
看護師、看護学生の皆さん、日々の臨床現場での学びをレポートにまとめる際、看護過程をどのように活かしていますか?看護過程は、患者さん一人ひとりに合わせた看護を提供する上で不可欠な思考のプロセスです。レポート作成においても、この看護過程に沿って記述することで、あなたの看護観や思考プロセスをより明確に伝えることができます。
ここでは、看護過程の各段階に沿ったレポート作成のポイントを、具体的な記述例を交えながら解説します。この情報を参考に、より深く、そして説得力のある看護レポートを作成しましょう。
看護過程の各段階(アセスメント、計画、実施、評価)
看護過程は、アセスメント(情報収集と分析)、計画(目標設定と看護介入計画の立案)、実施(計画の実行)、評価(効果の判定と改善)の4つの段階から成ります。それぞれの段階をレポートに落とし込むことで、あなたの看護の質を具体的に示すことができます。
- アセスメント:患者さんの状態を多角的に把握し、問題点を見つけ出す段階です。主観的情報(患者さんの訴え)と客観的情報(バイタルサイン、検査データなど)を収集し、分析します。
- 計画:アセスメントで得られた情報をもとに、看護目標を設定し、目標達成のための具体的な看護介入を計画します。
- 実施:計画に沿って看護介入を行います。その過程で、患者さんの反応を観察し、必要に応じて計画を修正します。
- 評価:看護介入の効果を評価し、目標達成度を判定します。達成できなかった場合は、原因を分析し、今後の計画に活かします。
各段階における記述例
各段階における具体的な記述例を通して、看護過程をレポートにどのように落とし込むのかを見ていきましょう。各段階でどのような情報を記述し、どのように表現すれば良いのかを学びましょう。
- アセスメント:例:「患者Aは、呼吸困難を訴え、SpO2 90%(室内気管)、チアノーゼを認めた。既往歴として慢性閉塞性肺疾患(COPD)があり、呼吸状態の悪化が疑われた。」
- 計画:例:「呼吸状態の改善を目標とし、体位変換、酸素投与(2L/分)、呼吸状態のモニタリングを実施する。また、患者の不安軽減のため、声かけを行う。」
- 実施:例:「体位変換を実施したところ、呼吸苦が軽減し、SpO2は94%に改善した。患者は『少し楽になった』と話した。酸素投与を継続し、呼吸状態を観察した。」
- 評価:例:「呼吸状態は改善したが、SpO2は目標値に達していないため、酸素流量の調整を検討する。患者の不安は軽減したが、さらなる情報収集が必要である。」
看護判断の明確化
看護レポートにおいて、あなたの看護判断を明確にすることは非常に重要です。アセスメントの結果からどのような問題点を見つけ、どのような根拠に基づいて看護計画を立案し、実施したのかを具体的に記述しましょう。
また、評価の結果から、なぜそのような判断に至ったのか、今後の課題は何なのかを明確にすることで、あなたの思考プロセスを効果的に伝えることができます。これにより、あなたの専門性が伝わり、レポートの質が格段に向上します。
学びと反省:自己評価の記述方法
看護師、看護学生の皆さん、実習や日々の業務を通して得た学びを、どのように自己評価としてまとめ、次へと繋げていますか?自己評価は、自身の成長を促すために非常に重要なプロセスです。ここでは、効果的な自己評価を行うための具体的な方法を解説します。自身の成長を客観的に評価し、更なるスキルアップを目指しましょう。
自己評価のポイント
自己評価を効果的に行うためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、具体的な事例に基づいて評価を行うことが重要です。抽象的な表現ではなく、実際に経験した出来事を基に、何がうまくいき、何が課題だったのかを具体的に記述します。
- 目標設定: 事前に立てた目標に対する達成度を評価します。目標設定が曖昧だと、評価も曖昧になりがちです。
- 根拠に基づいた評価: 感情的な判断を避け、客観的な根拠に基づいて評価を行います。例えば、患者さんの反応や、同僚からのフィードバックなどを参考にします。
- 多角的な視点: 自分の強みだけでなく、改善点や弱点も正直に評価します。自己肯定感を高めつつ、自己成長に必要な課題を見つけ出しましょう。
客観的な視点を取り入れる
自己評価を客観的に行うためには、多角的な視点を取り入れることが不可欠です。自己評価はどうしても主観的になりがちですが、以下の方法を試すことで、より客観的な評価が可能になります。
- 記録の活用: 実習記録や日誌、患者さんのカルテなどを参考に、具体的な行動や言動を振り返ります。
- フィードバックの収集: 指導者や同僚からのフィードバックを積極的に求めます。第三者の意見は、自分では気づかない視点を与えてくれます。
- 振り返りの習慣化: 定期的に自己評価を行う習慣をつけます。日々の記録を見返し、定期的に自己評価を行うことで、自身の成長を可視化できます。
具体的な改善策の記述
自己評価の最終的な目的は、今後の成長に繋げることです。そのため、改善点を明確にし、具体的な改善策を記述することが重要になります。改善策は、具体的で実行可能なものであるほど効果的です。
- 課題の特定: 評価を通じて見つかった課題を具体的に記述します。
- 目標設定: 課題を克服するための具体的な目標を設定します。目標はSMARTの法則(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限が明確)に基づいて設定すると効果的です。
- 行動計画: 目標を達成するための具体的な行動計画を立てます。いつ、何を、どのように行うのかを明確にします。
- 継続的な評価: 行動計画を実行し、定期的に進捗状況を評価します。必要に応じて計画を修正し、目標達成に向けて進みます。
自己評価は、自己成長を促すための重要なツールです。今回ご紹介したポイントを参考に、自身の学びを客観的に評価し、具体的な改善策を立て、更なるスキルアップを目指しましょう。
レポート全体の構成と流れ
看護レポートは、あなたの専門知識と経験を伝えるための重要なツールです。しかし、構成がしっかりしていなければ、伝えたいことがうまく伝わらないこともあります。ここでは、レポート全体の構成と、それをどのように流れるように記述していくかについて解説します。
導入の書き方
導入部分は、読者である指導者や教員に、あなたが何を報告したいのかを伝えるための最初のステップです。簡潔かつ明確に、レポートの目的と概要を示すことが重要です。
- 背景の説明: なぜこのレポートを書くのか、その背景を簡潔に説明します。
- 目的の提示: レポートを通して何を伝えたいのか、目的を明確にします。
- 概要の提示: レポート全体の構成を簡単に説明し、読者の理解を促します。
例えば、以下のように記述できます。「本レポートでは、〇〇病棟での実習を通して経験した、〇〇患者の看護事例について報告します。患者様の〇〇という課題に対し、看護過程に基づいた具体的なケアを提供し、その効果と課題について考察します。」
本論の展開方法
本論は、あなたの経験や考察を具体的に示す部分です。論理的な構成と、根拠に基づいた記述が求められます。
- 情報収集: 患者様の情報(病歴、現病歴、検査データなど)を整理し、客観的に記述します。
- アセスメント: 収集した情報をもとに、患者様の状態を分析し、看護問題点を明確にします。
- 計画: 看護目標を設定し、具体的な看護介入計画を立案します。
- 実施: 計画に基づいた看護ケアを具体的に記述します。
- 評価: 看護ケアの効果を評価し、結果を分析します。
各段階で、あなたの考えや判断を具体的に示し、なぜそのケアを選択したのか、どのような効果があったのかを説明することが大切です。
結論のまとめ方
結論は、レポート全体の要約であり、あなたの学びをまとめる部分です。
- 要約: レポートの主要な内容を簡潔にまとめます。
- 考察: 今回の経験から得られた学びや課題、今後の展望を述べます。
- 提言: 今後の看護実践に活かせる改善点や、さらに学びを深めるための課題を提示します。
結論は、あなたの成長を示す場でもあります。積極的に自己評価を行い、今後の看護に活かせるようにしましょう。
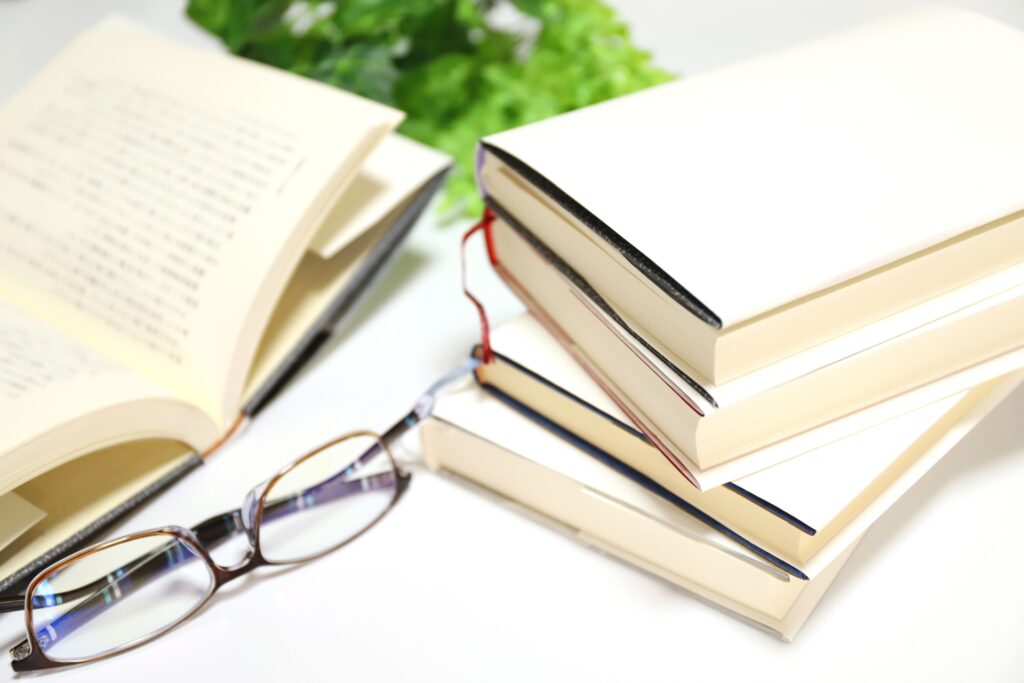
参考文献の書き方と引用方法
看護レポートを完成させる上で、参考文献の正確な記載と適切な引用は不可欠です。参考文献は、あなたのレポートの信頼性を高め、論拠を明確にするために重要です。ここでは、参考文献リストの作成から引用方法、スタイルガイドまで、詳しく解説します。
参考文献を正しく記載し、引用することで、あなたのレポートはより質の高いものへと進化します。正確な情報に基づいたレポートは、読み手の信頼を得て、あなたの看護師としての成長を後押しするでしょう。
参考文献リストの作成
参考文献リストは、レポートに引用したすべての情報源をまとめたものです。記載方法にはいくつかのルールがあり、これらに従うことが求められます。
- 著者名: 姓、名(イニシャル)の順で記載します。複数の著者がいる場合は、全員の名前を記載するか、主要な著者と「他」と表記します。
- 出版年: 論文や書籍が出版された年を記載します。
- タイトル: 論文や書籍のタイトルを記載します。
- 出版情報: 出版社名、出版地、論文が掲載されている雑誌名、巻号、ページなどを記載します。
これらの情報を正確に記載することで、読者は参考文献を特定しやすくなります。参考文献リストは、レポートの最後にまとめて記載するのが一般的です。
適切な引用方法
引用は、他者の著作物からアイデアや情報を借用する行為です。引用を行う際には、以下の点を守ることが重要です。
- 引用部分の明示: 引用部分を明確に示すために、引用符(「」または“ ”)で囲むか、字下げを行います。
- 出典の明記: 引用した情報源を、本文中に(著者名、出版年)のように記載します。
- 過度な引用の回避: 引用はあくまで補強材料であり、自分の意見や考察を主体とすることが重要です。
適切な引用は、あなたの論理を支え、レポートの信頼性を高めます。引用する際は、必ず出典を明記し、著作権を尊重しましょう。
参考文献のスタイルガイド
参考文献の記載方法には、様々なスタイルガイドが存在します。代表的なものに、MLA、APA、シカゴスタイルなどがあります。
これらのスタイルガイドは、それぞれ異なるルールを持っています。
- MLAスタイル: 主に人文科学分野で使用されます。
- APAスタイル: 心理学、教育学などの分野で広く使用されます。
- シカゴスタイル: 歴史学や社会科学分野で用いられます。
レポート作成の際には、指導教官や所属機関が推奨するスタイルガイドに従うようにしましょう。スタイルガイドに沿って参考文献を記載することで、レポート全体の統一感が生まれ、読みやすさが向上します。
完成度の高いレポート作成のための最終チェックポイント
看護レポートの執筆、お疲れ様でした。あなたの努力が詰まったレポートも、最終チェックでさらに完成度を高めることができます。ここでは、提出前に必ず確認しておきたいポイントをまとめました。これらのチェックリストを活用し、自信を持ってレポートを提出しましょう。
誤字脱字、文法チェック
レポートの信頼性を左右するのが、正確な文章表現です。誤字脱字や文法の間違いは、内容への理解を妨げるだけでなく、あなたの専門性への疑念を抱かせる可能性もあります。以下の点に注意して、丁寧にチェックを行いましょう。
- 誤字脱字のチェック: 誤字脱字は、手作業での確認に加え、Wordなどのソフトウェアの校閲機能も活用しましょう。氏名や専門用語など、特に間違いやすい箇所は念入りに確認してください。
- 文法・表記のチェック: 文法的な誤りがないか、句読点の使い方は適切か、表記ルール(「ですます調」と「である調」の混在など)に違反していないかを確認しましょう。
- 推敲: 一度書いた文章を読み返し、表現が分かりにくい箇所や冗長な箇所を修正しましょう。より簡潔で分かりやすい表現へと改善することで、レポートの質を格段に向上させることができます。
論理構成の確認
論理的な構成は、あなたの思考の整理力と、情報を伝える能力を評価する上で非常に重要です。レポート全体の構成を見直し、論理の飛躍がないか、各要素が整合性を持って配置されているかを確認しましょう。
- 構成全体のチェック: 導入から結論まで、論理的な流れで構成されているかを確認します。各章・節の関連性、情報の流れがスムーズであるかをチェックしましょう。
- 根拠と主張の整合性: 自分の主張を支える根拠(事例、データ、文献など)が適切に示されているかを確認します。根拠が曖昧な場合や、主張と根拠がずれている場合は、修正が必要です。
- 客観性の確保: 主観的な意見に偏りすぎていないか、客観的な視点も取り入れて多角的に考察できているかを確認しましょう。
適切な表現の確認
分かりやすく、正確な表現は、あなたの思考を的確に伝えるために不可欠です。専門用語の使用、表現の具体性、そして読みやすさという観点から、最終チェックを行いましょう。
- 専門用語の適切な使用: 専門用語の意味を正しく理解し、適切な場面で使用しましょう。多用しすぎると分かりにくくなるため、読者のレベルに合わせて調整することも重要です。
- 具体的な表現: 抽象的な表現を避け、具体的な事例やデータを用いて説明することで、説得力が増します。五感に訴えるような表現も効果的です。
- 読みやすさの向上: 文の長さ、段落の構成、漢字のバランスなどに気を配り、読みやすい文章を心がけましょう。句読点の使い方や、改行の位置も重要です。
これらのチェックポイントを一つ一つ確認することで、あなたのレポートはさらに洗練され、高い評価に繋がるはずです。自信を持って、レポートを完成させてください。
監修者プロフィール

宮本 大輔
聖ルチア病院、福岡県立精神利用センター太宰府病院にて勤務
2017年 リアン訪問看護 設立
2022年 ネクストリンク訪問看護 設立
2024年 地域創生包括支援協会 理事
【資格】
・看護師
・相談支援専門員
・サービス等管理責任者

出利葉 貴弘
-医療・福祉分野の情報発信とDX推進を担う事業責任者
株式会社LIH 代表取締役
-Webマーケター/コンテンツディレクター
福岡を拠点に、これまで500社以上のWeb制作・マーケティング支援を行ってきました。2025年より「訪問看護テックナビ」の責任者として、医療・福祉分野の情報発信やIT導入を推進しています。
訪問看護で働く方々や、利用者・ご家族のために、「わかりやすく信頼できる情報」を届けることが私たちの役割です。本サイトを通じて、現場を支える力になれれば幸いです。
【経歴】
2015年 個人事業にてWebマーケティング業を開始
2016年 アイティーラボ株式会社(久留米市) 設立
2018年 株式会社LIH(福岡市) へ社名変更
2025年 株式会社テックナビ 取締役就任「訪問看護テックナビプロジェクト開始」
【保有スキル・資格など】
・Web制作(ディレクション・設計・ライティング)
・SEOコンサルティング(実務10年以上)
・AI×業務効率化コンサル







