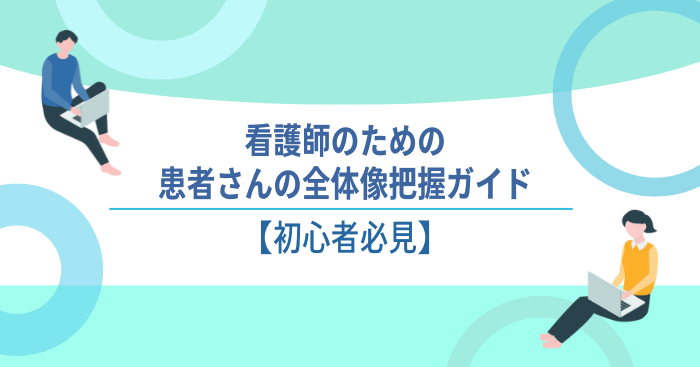看護師のための患者さんの全体像把握ガイド【初心者必見】
看護師として患者さんの全体像を把握することは、質の高いケアを提供するために不可欠です。患者さんの背景、身体状態、精神状態、社会状況などを理解することで、個別ニーズに合わせた適切な看護計画を立て、より良いケアを実現できます。
この記事では、看護における全体像の把握方法から、具体的な事例、そして看護計画への展開方法までを分かりやすく解説します。
看護における全体像把握の重要性
看護師として、患者さんの全体像を把握することは、質の高いケアを提供する上で基盤となるものです。患者さん一人ひとりを理解し、その人にとって最適な看護を提供するためには、多角的な視点と深い洞察力が不可欠です。ここでは、看護における全体像把握の重要性を、具体的な側面から掘り下げていきます。
質の高いケア提供のための基盤
患者さんの全体像を把握することは、単に病状や治療内容を理解するだけではありません。患者さんの生活背景、価値観、そして個々のニーズを理解することで、真に患者さん中心の看護を提供するための基盤となります。これにより、患者さんの満足度を高め、治療への積極的な参加を促し、最終的にはより良い健康状態へと導くことができます。
個別ケアプラン作成への貢献
患者さんの全体像を把握することで、画一的なケアではなく、個々の患者さんに合わせたケアプランを作成することが可能になります。それぞれの患者さんの状態、生活環境、価値観などを考慮したケアプランは、患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)の向上に大きく貢献します。具体的な目標設定、適切な看護介入、そして評価を組み合わせることで、より効果的なケアを提供できます。
患者さんとの信頼関係構築
患者さんの全体像を把握しようとする姿勢は、患者さんとの間に信頼関係を築く上で非常に重要です。患者さんは、自分のことを理解し、尊重してくれる看護師に対して、安心感を抱き、心を開きます。その結果、患者さんは自分の悩みや不安を打ち明けやすくなり、より積極的に治療に参加するようになります。信頼関係は、良好なコミュニケーションを促進し、より良い看護へとつながります。

患者さんの全体像を把握するためのアセスメント
患者さんの全体像を把握することは、質の高い看護を提供する上で非常に重要です。患者さんの心身の状態、生活背景、そして置かれている環境を多角的に理解することで、より適切な看護計画を立てることができます。以下に、患者さんの全体像を把握するための主要なアセスメント方法を詳しく見ていきましょう。
身体的アセスメント
身体的アセスメントは、患者さんの健康状態を評価するための基本的なプロセスです。バイタルサインの測定から始まり、全身の状態を観察し、異常の早期発見に努めます。
- バイタルサインの測定: 体温、脈拍、呼吸数、血圧などを測定し、患者さんの基本的な状態を把握します。
- 全身の観察: 患者さんの外観、皮膚の状態、呼吸の状態、排泄の状態などを観察し、異常の兆候がないか確認します。
- 系統的な聴診・触診: 呼吸音、心音、腹部の音などを聴診し、異常音の有無を確認します。また、触診によって、腫脹や圧痛の有無を評価します。
これらのアセスメントを通じて、患者さんの身体的な問題を早期に発見し、適切な治療や看護に繋げることが可能になります。
精神・心理的アセスメント
精神的・心理的アセスメントは、患者さんの心の状態を理解するために不可欠です。患者さんの感情、思考パターン、認知機能を評価し、精神的なサポートの必要性を判断します。
- 精神状態の評価: 患者さんの気分、感情、思考、知覚などを評価します。不安や抑うつ、幻覚などの兆候がないか注意深く観察します。
- 認知機能の評価: 意識レベル、見当識、記憶力、理解力などを評価します。認知症やせん妄の早期発見に繋がります。
- コミュニケーション能力の評価: 患者さんのコミュニケーション能力を評価し、意思疎通の困難さがないかを確認します。
精神的・心理的アセスメントを通じて、患者さんの心の健康状態を把握し、必要に応じて精神科医やカウンセラーとの連携を図ることが重要です。
社会的アセスメント
社会的アセスメントは、患者さんの社会的な側面を理解するために行われます。患者さんの家族関係、経済状況、生活環境などを把握し、社会的なサポートの必要性を評価します。
- 家族関係の評価: 患者さんの家族構成、家族との関係、家族からのサポートの有無などを評価します。
- 経済状況の評価: 患者さんの経済的な問題の有無、生活費の確保状況などを評価します。
- 生活環境の評価: 患者さんの居住環境、近隣関係、地域社会との繋がりなどを評価します。
社会的アセスメントの結果に基づいて、ソーシャルワーカーや地域のサポート機関との連携を図り、患者さんが安心して生活できるような支援を提供します。
スピリチュアルアセスメント
スピリチュアルアセスメントは、患者さんの価値観や信仰、人生観を理解することを目的とします。患者さんの心の支えとなるものや、人生に対する意味を見出す手助けを行います。
- 価値観の探求: 患者さんの人生観、価値観、信条などを探求し、何が患者さんにとって大切なのかを理解します。
- 信仰の理解: 患者さんの宗教や信仰について尋ね、精神的な支えとなっているものを理解します。
- 人生の意味の探求: 患者さんが人生にどのような意味を見出しているのかを探求し、心の安寧をサポートします。
スピリチュアルアセスメントを通じて、患者さんの精神的なニーズに応え、心のケアを提供します。

アセスメント情報の整理と問題点の明確化
患者さんの情報を収集したら、次はそれらを整理し、問題点を明確にする段階に入ります。このプロセスは、質の高い看護計画を立案するための重要な基盤となります。情報を適切に整理し、患者さんの抱える問題を正確に把握することで、効果的なケアを提供できるようになります。
ゴードン機能健康パターン
ゴードン機能健康パターンは、患者さんの健康状態を包括的に評価するためのフレームワークです。このパターンを用いることで、患者さんの日常生活における11の機能領域を評価し、多角的な視点から問題点を把握することができます。 ゴードン機能健康パターンは、以下の11のパターンから構成されています。
- 健康知覚 – 健康管理: 健康に対する認識、健康管理行動
- 栄養 – 代謝: 食事摂取、水分摂取、栄養状態、皮膚の状態
- 排泄: 便通、排尿、発汗
- 活動 – 運動: 運動能力、日常生活動作(ADL)、レクリエーション
- 睡眠 – 休息: 睡眠の質、休息のパターン
- 認知 – 知覚: 感覚、認知機能、言語
- 自己知覚 – 自己概念: 自己認識、感情、ボディイメージ
- 役割 – 関係: 社会的役割、人間関係
- 性 – 生殖: 性的な側面、生殖機能
- コーピング – ストレス耐性: ストレスへの対処方法、問題解決能力
- 価値観 – 信念: 価値観、宗教、人生観
このパターンに沿って情報を整理することで、患者さんの強みと弱みを明らかにし、問題点を特定することができます。
関連図の作成
関連図は、アセスメント情報を視覚的に整理し、問題間の関連性を明確にするためのツールです。情報を整理し、問題間の関連性を視覚的に表現することで、看護師は患者さんの全体像をより深く理解し、適切な看護介入を計画することができます。 関連図を作成する際には、以下の手順で行います。
- 情報の収集: 患者さんのアセスメント情報をすべて書き出します。
- 問題の特定: 患者さんの問題点を特定し、中心となる問題を選びます。
- 関連性の分析: 各情報と問題点との関連性を分析し、矢印でつなぎます。
- 問題の優先順位付け: 問題の緊急度や重要度に応じて、優先順位をつけます。
- 関連図の完成: 関連図を完成させ、看護計画に役立てます。
関連図を作成することで、問題の原因や影響を視覚的に理解し、多角的な視点から看護計画を立案することができます。
看護診断の立案
看護診断は、患者さんの健康問題に対する看護師の専門的な判断を表現したものです。アセスメント情報を基に、患者さんの問題を明確にし、適切な看護介入を行うために不可欠です。
看護診断の分類
看護診断は、NANDA-I(北米看護診断協会)によって分類されています。NANDA-Iの分類に基づき、患者さんの問題点を正確に表現し、適切な看護介入を選択することができます。 看護診断は、以下の3つの要素で構成されます。
- 問題(Problem): 患者さんの健康状態や問題点を表す
- 原因(Etiology): 問題を引き起こす要因
- 徴候・症状(Signs and Symptoms): 問題を裏付ける根拠となる情報
これらの要素を組み合わせることで、患者さんの問題を具体的に表現した看護診断を立案できます。
適切な看護診断の選択
適切な看護診断を選択するためには、アセスメント情報に基づいて、患者さんの問題を正確に捉える必要があります。NANDA-Iの看護診断リストを参照し、最も適切な診断を選択します。 診断を選択する際には、以下の点に注意しましょう。
- 患者さんの問題に合致しているか
- 看護師が介入できる問題であるか
- 患者さんのニーズを適切に反映しているか
看護診断を立案することで、看護師は患者さんの問題に対する具体的な目標を設定し、効果的な看護計画を立案することができます。
看護計画の作成
看護計画は、患者さんの状態を良くし、目標を達成するために不可欠です。患者さんのニーズに応じた具体的な計画を立てることで、より質の高い看護を提供できます。この章では、看護計画の立て方について詳しく見ていきましょう。
短期目標と長期目標の設定
看護計画を立てる上で、まず重要になるのは目標設定です。目標には、短期目標と長期目標があります。短期目標は、数日〜1週間程度で達成可能な目標であり、患者さんの具体的な問題点に対する改善を目指します。一方、長期目標は、数週間〜数ヶ月かけて達成を目指す目標で、患者さんの全体的な健康状態の改善やQOL(生活の質)の向上を目指します。
- 短期目標の例:痛みスケールが下がる、体温が平熱に戻る
- 長期目標の例:自立した日常生活を送れるようになる、社会復帰を果たす
目標設定の際には、SMARTの原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:時間制約がある)を意識することが重要です。これにより、目標が明確になり、達成度を評価しやすくなります。
看護介入の選択と根拠
目標が定まったら、次に具体的な看護介入を決定します。看護介入とは、目標達成のために行う具体的な看護活動のことです。例えば、痛みがある患者さんに対しては、薬物療法、温罨法、体位変換など、様々な介入方法が考えられます。
それぞれの介入方法には、必ず根拠(エビデンス)が必要です。なぜその介入が効果的なのか、科学的な根拠に基づいて説明できるようにしましょう。根拠に基づいた看護は、より安全で効果的なケアを提供するための基盤となります。
計画の実行と評価
看護計画を実行に移す際には、患者さんと協力し、計画に沿ってケアを進めていきます。患者さんの状態を観察し、計画通りに進んでいるか、目標が達成されそうかなどを評価します。評価の結果に基づいて、必要であれば計画を修正します。
計画の評価は、看護の質を向上させるために非常に重要です。計画がうまくいかなかった場合は、なぜうまくいかなかったのかを分析し、次の計画に活かしましょう。計画の実行と評価を繰り返すことで、より良い看護を提供できるようになります。
個別ケアプラン作成のポイント
個別ケアプランを作成する際には、以下の点を意識しましょう。
- 患者さんの個別性を考慮する
- 患者さん自身の意向を尊重する
- 多職種との連携を図る
- 記録を正確に残す
目標達成のための効果的な介入方法
効果的な介入方法を選択するためには、患者さんの状態を正確に把握し、科学的根拠に基づいた方法を選択することが重要です。また、患者さんとのコミュニケーションを通して、患者さんの意向や価値観を理解し、それに沿った介入を行うことが大切です。
看護記録の重要性
看護記録は、看護計画の実行状況や患者さんの状態変化を記録する上で不可欠です。正確な記録は、多職種との情報共有を円滑にし、チーム全体で質の高いケアを提供するための基盤となります。また、記録は、看護師自身の振り返りや学びにも役立ちます。
チーム医療との連携と看護記録
患者さん中心の看護を実現するためには、多職種との連携が不可欠です。医師をはじめ、理学療法士、作業療法士、栄養士など、様々な専門家と情報を共有し、協力して患者さんのケアにあたることで、より質の高い医療を提供できます。
チーム医療における看護師の役割は、患者さんの状態を多角的に把握し、その情報をチーム全体で共有することです。この章では、チーム医療における連携の重要性と、そのための具体的な方法について解説します。
医師や他職種との情報共有
チーム医療を円滑に進めるためには、各職種間の情報共有が不可欠です。看護師は、患者さんの日常生活の様子や病状の変化を最も身近で観察しているため、得られた情報はチームにとって非常に貴重なものとなります。具体的には、以下のような方法で情報共有を行います。
- ラウンドへの参加: 医師や他の医療従事者と共に行う回診に参加し、患者さんの状態を直接報告し、意見交換を行います。
- カンファレンスの開催: 定期的に多職種が集まり、患者さんの治療方針やケアについて話し合うカンファレンスを開催します。
- 電子カルテの活用: 電子カルテに患者さんの情報を正確かつ詳細に記録し、チーム全体で共有します。
情報共有の際には、客観的な事実に基づいた情報を伝えることが重要です。個人的な意見や推測ではなく、観察した事実を具体的に伝え、他の職種が患者さんの状態を正確に把握できるように努めましょう。
カンファレンスの重要性
カンファレンスは、チーム医療において重要な役割を果たします。カンファレンスを通じて、各職種がそれぞれの専門知識を活かし、患者さんの状態を多角的に評価し、より適切なケアプランを立案することができます。また、カンファレンスは、チーム内のコミュニケーションを活発にし、相互理解を深める機会にもなります。
カンファレンスを効果的に行うためには、以下の点に注意しましょう。
- 目的の明確化: カンファレンスの目的を明確にし、議題を事前に共有することで、効率的な議論を促します。
- 積極的な発言: 各職種が積極的に発言し、それぞれの専門的な視点から意見を出し合うことで、多角的な視点からの評価が可能になります。
- 決定事項の共有: カンファレンスで決定した事項は、必ずチーム全体で共有し、それぞれのケアに反映させます。
効果的なコミュニケーションスキル
チーム医療における効果的なコミュニケーションは、質の高いケアを提供する上で不可欠です。看護師は、患者さんやその家族、そしてチーム内の他の職種との間で、円滑なコミュニケーションを図る必要があります。効果的なコミュニケーションスキルを身につけるためには、以下の点を意識しましょう。
- 傾聴: 相手の話を注意深く聞き、理解しようと努める姿勢が大切です。相手の言葉だけでなく、表情や態度からも情報を読み取りましょう。
- 明確な表現: 自分の考えや情報を、分かりやすく、正確に伝えることが重要です。専門用語を避け、平易な言葉で説明するよう心がけましょう。
- 非言語的コミュニケーション: 言葉だけでなく、身振り手振りや表情、声のトーンなどもコミュニケーションに影響を与えます。相手に合わせた適切な非言語的コミュニケーションを意識しましょう。
- アサーション: 自分の意見を尊重しつつ、相手の意見も尊重する、建設的なコミュニケーションスタイルを身につけましょう。
効果的なコミュニケーションスキルを身につけることで、チーム内の連携を強化し、患者さん中心のケアをより効果的に実践することができます。

まとめ:患者中心の看護の実践に向けて
この記事を通じて、看護における患者さんの全体像把握の重要性から、具体的な実践方法、そしてチーム医療との連携に至るまでを解説しました。看護師の皆様が、患者さん一人ひとりに寄り添い、より質の高い看護を提供できるよう、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
継続的な学習の重要性
医療は常に進化しており、新しい知識や技術が次々と生まれています。看護師として、患者さんの全体像を正確に把握し、適切なケアを提供するためには、継続的な学習が不可欠です。日々の業務の中で疑問に思ったことや、新しい情報に触れた際には、積極的に学習し、知識を深めていく姿勢が大切です。
学習方法としては、研修への参加、専門書籍の購読、学会への参加などが挙げられます。また、同僚との情報交換や、経験豊富な先輩看護師からのアドバイスも、貴重な学びの機会となります。常に学び続けることで、患者さんの多様なニーズに応えることができるようになります。
自己研鑽の必要性
自己研鑽は、看護師としての専門性を高める上で非常に重要です。自己研鑽を通じて、自身の強みや弱みを理解し、改善点を見つけ出すことができます。自己研鑽の方法は多岐にわたりますが、自身のキャリアプランや興味関心に合わせて、最適な方法を選択することが大切です。
自己研鑽の例としては、専門看護師や認定看護師の資格取得、研究活動への参加、論文発表などが挙げられます。また、日々の業務の中で、患者さんとのコミュニケーションスキルを磨いたり、新しい看護技術を習得したりすることも、自己研鑽につながります。自己研鑽を通じて、看護師としての自信を高め、より質の高いケアを提供できるよう努めましょう。
倫理的配慮
看護師は、倫理的配慮に基づいた看護を提供することが求められます。患者さんの尊厳を守り、個々の価値観を尊重することは、看護の基本です。患者さんのプライバシー保護、インフォームドコンセントの徹底、そして自己決定を支援することは、倫理的配慮の重要な要素です。
倫理的ジレンマに直面した場合は、一人で抱え込まず、同僚や上司、倫理委員会などに相談することが重要です。倫理的な問題に対する正しい判断は、患者さんの最善の利益を守り、信頼関係を築くために不可欠です。常に倫理的価値観を意識し、患者さんにとって最善のケアを提供できるよう努めましょう。
看護師として、患者さんの全体像を把握し、患者さん中心の看護を実践することは、容易なことではありません。しかし、日々の努力と学びを通じて、必ず実現できます。この記事が、皆様の看護実践の一助となり、患者さんとそのご家族の笑顔につながることを願っています。
監修者プロフィール

宮本 大輔
聖ルチア病院、福岡県立精神利用センター太宰府病院にて勤務
2017年 リアン訪問看護 設立
2022年 ネクストリンク訪問看護 設立
2024年 地域創生包括支援協会 理事
【資格】
・看護師
・相談支援専門員
・サービス等管理責任者

出利葉 貴弘
-医療・福祉分野の情報発信とDX推進を担う事業責任者
株式会社LIH 代表取締役
-Webマーケター/コンテンツディレクター
福岡を拠点に、これまで500社以上のWeb制作・マーケティング支援を行ってきました。2025年より「訪問看護テックナビ」の責任者として、医療・福祉分野の情報発信やIT導入を推進しています。
訪問看護で働く方々や、利用者・ご家族のために、「わかりやすく信頼できる情報」を届けることが私たちの役割です。本サイトを通じて、現場を支える力になれれば幸いです。
【経歴】
2015年 個人事業にてWebマーケティング業を開始
2016年 アイティーラボ株式会社(久留米市) 設立
2018年 株式会社LIH(福岡市) へ社名変更
2025年 株式会社テックナビ 取締役就任「訪問看護テックナビプロジェクト開始」
【保有スキル・資格など】
・Web制作(ディレクション・設計・ライティング)
・SEOコンサルティング(実務10年以上)
・AI×業務効率化コンサル